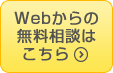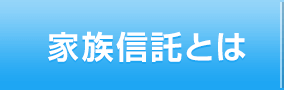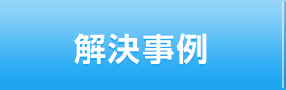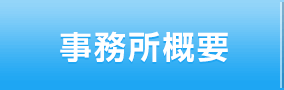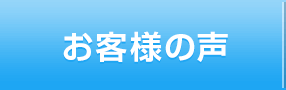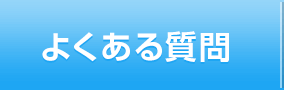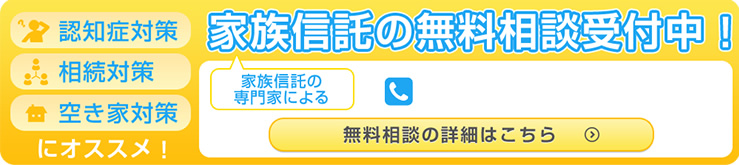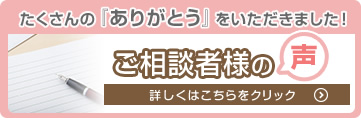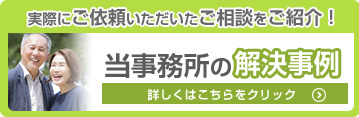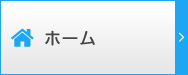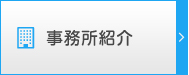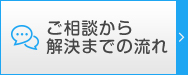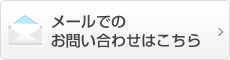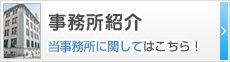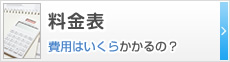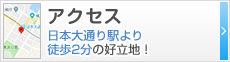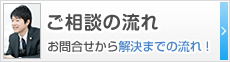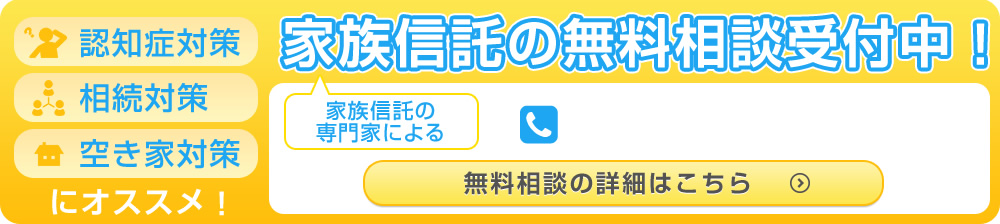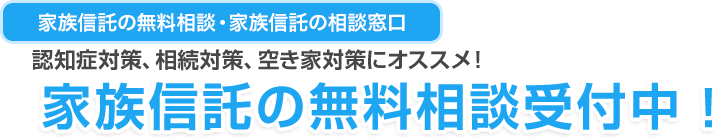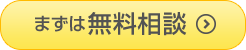認知症の方の預金でも、親族の代理出金が可能になったのですか?
令和3年2月18日、一般社団法人全国銀行協会が、認知症患者の預金についても、親族による代理出金が考えられる旨の見解を発表しました。
「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」(※以下「考え方」とします)
但し、以下の2点には、注意が必要です。
①認められるのは、極めて限定的な対応であること。
②金融機関に対し、この考え方に従った一律の対応を求めるものではないこと。
よって、いざという時、間違いなく預金の引出しを行えるようにするには、後見制度を利用するか、将来出金が必要になりそうな大きなお金を民事信託をしておくなど、対策が必要となることは変わりません。
目次
①認められるのは、極めて限定的な対応であること。
認知症患者の預金について、親族による代理(=無権代理)出金が無制限に認められるものではなく、むしろ、代理出金出来るのは極めて例外的な場合のみであることには要注意です。
先ほどの考え方でも、
「親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応」
「本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる」
とされています。
②金融機関に対し、この考え方に従った一律の対応を求めるものではないこと。
また、仮に、この「考え方」に当てはまる場合であったとしても、各金融機関が出金依頼に応じるかは別問題であることにも、注意が必要です。
一般社団法人全国銀行協会は、この考え方の発表にあたり、
「本考え方は、会員各行の参考となるよう取りまとめたものであり、会員各行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況等により、本考え方と異なる対応が取られるケースもあり得る」
としているほか、
考え方本文でも、
「銀行としてより厳格な対応を行うケースや、取引のリスクが大きいと判断された場合に取引を謝絶するケースはあり得る」としています。
まとめ①(事前対策なく判断能力が低下した場合)
今回の「考え方」でも、やはり、ご本人の認知判断能力が低下した場合には、
「成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である」
と明記されており、いざという時、間違いなく預金の引出しを行えるようにするには、後見制度を利用するか、将来出金が必要になりそうな大きなお金を民事信託をしておくなど、対策が必要となることは変わりません。
日弁連意見書
【2021/6/22加筆】
その後、日本弁護士連合会が、一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」についての意見書を取りまとめ、一般社団法人全国銀行協会に提出しました。
この意見書では、認知度高齢者の方に代わってご親族が預貯金の払出しや振込依頼を行うこと(=親族等による無権代理取引)に金融機関が応じることのリスクが強調されており、今後、金融機関がより慎重な対応になることも想定されますので、
今後の金融機関の対応を確認しつつ、是非、しっかりと生前対策を進めていただければと思います。
予約型代理人(事前対策の新たな選択肢)
以上は、事前の対策をせずに、判断能力が低下してしまった場合の対応についてでした。
これに対して、判断能力低下前の、事前対策の新たな選択肢として、令和3年3月8日、
株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
株式会社三菱 UFJ 銀 行
三 菱 UFJ 信託銀行株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
が、「予約型代理人」サービスの導入について、公表しました。
「お客さまご本人の認知・判断機能が低下し、ご本人による金融取引ができなくなる場合に備え、将来、お客さまご本人の代わりにお取引いただく代理人を指定できるサービス」とのことです(上記公表資料より)。
日常生活で必要な少額の入出金については、このサービスを活用していくことが考えられます。
なお、上記公表資料によると、「代理人ができる対象手続き」に関し、例えば、運用性商品(外貨預金・投資信託・株式等)については「売却・解約」に限定されており「購入」が除かれているなど、実際に代理人がどこまで手続きを行えるのかは、事前に確認しておく必要がありそうです。
まとめ②(事前対策について)
以上のとおり、金銭管理についての事前対策については、任意後見制度、信託銀行等の金銭信託(商事信託)、家族信託(民事信託)に加えて、予約型代理人も加わり、複数の選択肢を選べる時代になってきました。
それぞれのメリット・デメリットを比較して、最善の選択をして頂ければ幸いです。
同じカテゴリのQ&A